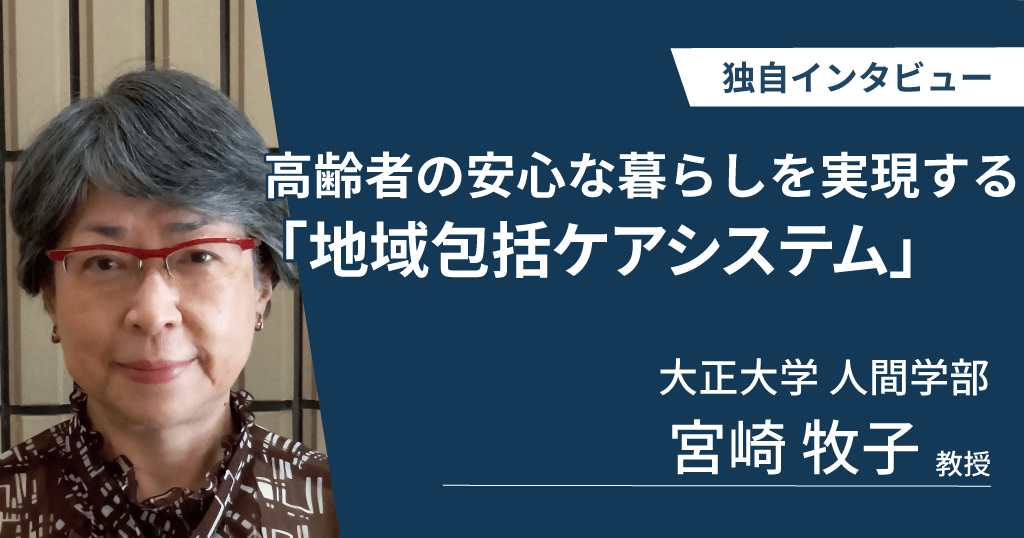少子高齢化が進む現代社会では、高齢者の介護負担や貧困問題といったさまざまな課題が見えてきました。
こういった中で高齢者が安心して暮らせる社会を実現させるためには「地域包括ケアシステム」というものが重要になってきます。
この記事では、大正大学の宮崎牧子教授に、高齢者の安心な暮らしを実現できる「地域包括ケアシステム」とはどういったものかについて独自インタビューさせていただきました。

大正大学 人間学部 社会福祉学科
宮崎牧子(みやざき まきこ)教授
日本女子大学文学部社会福祉学科を卒業後、1986年に日本女子大学大学院社会福祉学専攻を修了。その後、社会福祉法人東京弘済園非常勤職員、介護福祉士養成の専門学校教員を務める。
1997年より大正大学人間学部社会福祉学科専任講師・助教授を経て、2006年より現職。その他、全国老人福祉問題研究会事務局長、日本ソーシャルワーカー協会副会長、区民ひろば西巣鴨運営協議会委員などを兼任。
研究分野は社会福祉。主に高齢者福祉・地域福祉に焦点を当てて研究している。
日本の高齢者福祉における課題とは
TLG GROUP編集部:最近は高齢者の孤立や貧困問題などが取り沙汰されていますが、実際の日本における高齢者福祉の課題というのはどういったものなのでしょうか。
宮崎教授:そうですね。現在は一人暮らしの高齢者が多くなってきているので、社会的孤立というものが課題となってきています。
一人暮らしだと孤立してしまうことはよくあるのですが、高齢者の場合だとただ単に孤立するのではなく、社会的孤立になってしまうところが非常に大きな課題です。
また、社会的孤立に陥りやすいのは一人暮らしの高齢者だけではありません。高齢者の夫婦の世帯や子どもと一緒に暮らしている世帯でも社会的孤立に置かれてしまうケースが多くなってきています。
TLG GROUP編集部:子どもがいる世帯というと、具体的にどういった経緯で社会的孤立の状態になってしまうのでしょうか。
宮崎教授:最近ニュースや新聞でも良く報道されているのですが、「8050問題」のケースがそれに当たります。8050問題というのは、高齢になった親が40代、50代の子ども世代を経済的・精神的に支えて生活していることを言います。
高齢の親が元気であれば何とか生活できるのですが、親が病気になったり、片方が亡くなったりすると子どもを支えきれなくなってしまい、孤立してしまうことがあるのです。
また、親が倒れてしまうと子どもも生活が維持できなくなってしまいます。こうした問題もあり、高齢者の社会的孤立はどんどん広まっているのです。
TLG GROUP編集部:確かに近年は8050問題による事件を聞いたことがあります。高齢者夫婦が社会的に孤立してしまうのも似たような状態に陥ってしまうからでしょうか。
宮崎教授:そうですね。隣近所の人と関わることなく夫婦で何とか助け合って生活していると、どちらかが認知症になったり身体的な障害を負ったりした場合に社会的孤立の状態になってしまいます。
また、歳を取っていく中で5年前はできたことができなくなってしまい、夫婦だけで生活することが難しくなってしまう場合もあります。
ところが、隣近所の人とは関わりがないので、夫婦の様子は誰にも分かってもらえないままなのです。その結果、大変な状況になって初めて近所の方々が夫婦の生活に気づくというケースが増えてきています。これは地方でも都会でも変わらないですね。
TLG GROUP編集部:周りの方が気づけない状況にあるという点は非常に大きな問題ですね。個人的な印象ではありますが、近年は自助努力が重視されすぎて他人に支援を求めづらいという方も増えてきているように思います。
実際、現在の支援制度も自助努力が第一で、努力でどうにもできなかったらようやく公的な制度が受けられるという風な形になってしまっているのでしょうか。
宮崎教授:そうですね。国の考えとしても自助努力が重要視されていると思います。だからと言って、制度やサービスを利用しないことが良いとは決して思いません。
ただ、元気なうち、ある程度若い年齢の時から近隣の方と挨拶するような関係を作っておくことはとても大切だと思います。
TLG GROUP編集部:なるほど。地域の方との関係性を築くことが社会的孤立を防ぐ第一歩になるのですね。
宮崎教授:最近は地震が増えてきましたよね。そういった時に「昨日の地震は大丈夫でしたか」という風に話したり、道で会った時に挨拶できたりということができる地域づくりを心がけていくことで、社会的孤立の状態にならないのではないかと思います。
TLG GROUP編集部:40代、50代の方でしたらそういった声掛けは比較的やりやすいのかなと思います。PTAに参加している方もそうですよね。
ただ、高齢者の方は地域での関りを持つために、何らかのコミュニティに参加する必要がありそうです。そういった点で言うと、地域の方との関係性を築くのもハードルが高いように感じます。
宮崎教授:そうですね。ただ、今は高齢者クラブ(老人クラブ)というものが各自治体にあるので、そういったところに参加してみるのも良いかなと思います。
高齢者クラブでは、高齢の方たちがその地域、町会の中で趣味活動やお誕生日会などを開いて元気にしているかを確認しあっています。
そういったものに加入されると、地域の中で顔なじみの友人を作ることもできますし、あるいはそういうことを超えて、地域の中で共通する楽しみを見つけられると思います。
また、今は公共の場を借りてクラブ活動ができる時代にもなってきているので、ぜひ「○○を一緒にやりませんか」と手を挙げて人を集めてみてほしいです。
元気な時からそうしていれば、病気になってしまった時でも地域の中で心配してくれる、声をかけてくれる人が自然な形でできるのではないかと思います。
TLG GROUP編集部:高齢者クラブへの参加は心身ともに良い影響を与えてくれそうですね。地域での声掛けが少なくなりつつある現代だからこそ、こういった活動は大切にしていきたいです。
高齢者が安心して暮らすために必要な体制整備
TLG GROUP編集部:高齢者クラブのお話もそうですが、高齢者の方、認知症の方が安心して暮らすためには何らかの支援や施策が必要になるかと思います。
具体的に、これからどのような支援や制度が必要になっていくのかという見通しはあるのでしょうか。
宮崎教授:そうですね。高齢者の方、認知症の方が以前と変わらない生活が送れるような買い物や食事作り、お金の出し入れの支援が必要になると思います。
つまり、高齢者の立場から見て、安心して支援してもらえるような体制づくりが大切になってくるのです。
最近は、歳を取ったり認知症になったりしてもリハビリなどを通じて地域の中で生活できるような状況になりつつあります。そのため、全面的に介護するのではなく、生活の細かな部分を支えていけるようにしていく必要があるのではないかと思います。
TLG GROUP編集部:ありがとうございます。日々の細かな支援というのは大切ですね。
課題の1つに「周りの方が高齢世帯の状況に気づけない」というものがありましたが、この課題を改善するためにはやはり公共的なサービスが必要になってくるのでしょうか。
宮崎教授:そうですね。しかし、介護保険制度における利用抑制や自治体からの支援というのは財源問題などで難しいところがあります。そのため、まずは地域の中で助け合う仕組みを作ることが第一になると思います。
その後、高齢者の方たちを支えることができる取り組みなどができてきたら、行政に働きかけてその仕組みを支える財源を支援してもらうという形が良いでしょう。
今の時代、最初から行政に支援してもらうのは難しいです。そのようなことから、地域の中で助け合いの取り組みを行い、「この取り組みを続けるために何割かは行政で支援してください」という話し合いを積み上げていく必要があるでしょう。
TLG GROUP編集部:地域の中での助け合いはとても大切ですよね。ただ、高齢者の方への支援となると、その人が本当に求めている支援なのかが分からないという不安があります。
実際、高齢者の方から支援が迷惑だと思われないようにするためのボーダーラインはどのように決めれば良いのでしょうか。
宮崎教授:確かに、行き過ぎた支援や高齢者側が求めていないことまでやってしまうのは避けたいですよね。その見極めにこそ社会福祉士や医療関係者といった専門家に相談してほしいと思います。
地域の中での助け合いは大事ですが、決して住民の人たちだけの組織ができれば良いというわけではありません。
専門家の組織と連携して、取り組みに対するアドバイスをもらえるのがベストだと思います。
TLG GROUP編集部:専門家に聞くことで、支える側の方たちの負担を減らすことができるのですね。様々な組織と連携することで、支援を受ける側の方たちも一人の人間として尊重されるような関係性を築いていけるのだということが分かりました。
高齢化社会における「地域包括ケアシステム」とは
TLG GROUP編集部:ここまで理想の福祉制度について伺ってきましたが、宮崎様が研究されている中で有効だと感じた市区町村の取り組みなどはあるのでしょうか。
宮崎教授:有名ですが、世田谷区は住民の活動が非常に盛んで、高齢者の方に対するサービスが充実していると思います。
また、鳥取県のある地域の取り組みも印象的でした。そこでは、空き家を有効活用して支援が必要な方の集合住宅を作ろうとしているのです。支援が必要な方が点在していると、移動にも時間がかかってしまいますし、場所によっては行くことができない場合があります。
こういった方々が共同住宅という形で過ごしていれば、適切なタイミングで支援することができますし、支援する側の負担も減りますよね。
このように、地域の事情や特色を考慮した支援の体制づくりをしている市区町村は理想的なモデルケースだと思います。
TLG GROUP編集部:統一した体制を適用するわけではなく、その地域に住む人々に合わせて体制を変えていかなければならない点はとても大切ですね。
宮崎様が担当されているゼミでも高齢者の方に向けた支援をされていると伺ったことがありますが、現在はどのようなことをされているのでしょうか。
宮崎教授:現在は、「学生出前定期便」という活動を学生と一緒にしています。これは学生によるインフォーマルな活動です。
具体的には、大正大学がある周辺地域にお住いの高齢者の方に、ちょっとした困りごとが起きたとき、学生がその方のお家を訪問して、困りごとを手助けしています。よく依頼されるのは、庭の草むしりや高いところの掃除ですね。
他にも、大正大学がある西巣鴨にも高齢者クラブがあるので、そこに大学生が参加することがあります。高齢者の方も「年齢が近い者同士で交流するのも楽しいけれど、大学生が加わるともっと楽しい」と言ってくれていますね。
TLG GROUP編集部:高齢者クラブではどのような交流をされているのでしょうか。
宮崎教授:去年は学生によるスマホ教室を開催しました。スマートフォンの基本的な使い方もそうですが、もっときれいに写真を撮る方法であったり、写真の保存方法だったりも教えていましたね。
TLG GROUP編集部:とても素敵な取り組みですね。こういった活動は宮崎様からご提案されて始められたのですか。
宮崎教授:14、15年前に地域の方とお話しする機会があり、その中で「高齢者の方が困っている」という話がきっかけで始まりましたね。
TLG GROUP編集部:そうだったのですね。15年も活動が続いているのはすごいです。
宮崎教授:こういった取り組みの主体は学生ですが、豊島区にはコミュニティソーシャルワーカーという社会福祉協議会の職員がいるので、その方々に活動をバックアップしてもらっています。
例えば、学生が訪問先の高齢者の方で心配だなと思う点があれば、コミュニティソーシャルワーカーに連絡して、その方と連絡を取っていただくのです。
学生出前定期便はちょっとした困りごとを学生が解決するという活動ですが、この取り組みを通じて高齢者の方と行政・専門職との橋渡しができるようになりました。
TLG GROUP編集部:専門家からのバックアップがあるのは心強いですね。ここまでのお話にあった市区町村や学生の取り組みといったものが、「地域包括ケアシステム」と言っても良いのでしょうか。
宮崎教授:そうですね。地域包括ケアシステムというのは自助・互助・公助・共助という役割が連携していくことによって作られています。
私どもが活動している西巣鴨地域の地域包括ケアシステムの中では、互助活動の1つとして学生出前定期便が位置付けられているのです。
学生による活動はあくまでインフォーマルなものということもあり、小さなことしかできません。
しかし、若い人が大勢いるという地域の特色を地域包括ケアシステムの中で活かせている事例でもあるのかなと思っています。
TLG GROUP編集部:ありがとうございます。それでは最後に、社会福祉に関心を持っている方や高齢者の方と一緒に暮らしている方に向けてメッセージをいただけますでしょうか。
宮崎教授:高齢者の方々もいきなり重介護が必要になるということはあまりありません。徐々に介護・介助が必要になってくることが多いので、最初はちょっとしたことに対応できるよう、家族や地域の中で取り組んでいただければと思います。
また、そういった取り組みも住民だけで背負う必要はありません。行政に取り組みを報告したり、対話をしたりしてより良い体制づくりをしていくことが大切です。
まとめ
TLG GROUP編集部:本日はお時間をいただき、ありがとうございました。宮崎教授にインタビューして、下記のことが分かりました。
- 現代の日本における高齢者福祉の課題は、社会的孤立に陥りやすい状況であるということ。
- 社会的孤立を防ぐためには地域との交流やコミュニティへの参加が重要である。
- 高齢者支援の体制を整備していくためには、地域での声掛けや行政との対話が必要である。
- 高齢者支援は地域住民だけでなく、専門家と連携して行うことが大切である。
- 地域包括ケアシステムとは自助・互助・公助・共助といった役割が連携することによって作られるものである。
少子高齢化が進む中、社会的孤立の状況に陥ってしまうのは非常に身近な問題となりました。こういった現状を少しでも改善していくためには、他者との交流や助け合いが欠かせません。
また、今回のインタビューではより良い社会を実現するために協力・連携が必要不可欠であるということが分かりました。
社会福祉に関心がある方だけでなく、その土地に住む方がどのように地域に貢献できるかを今一度見直してみる必要があるのではないでしょうか。
取材・文:TLG GROUP編集部
記事公開日:2024年5月16日