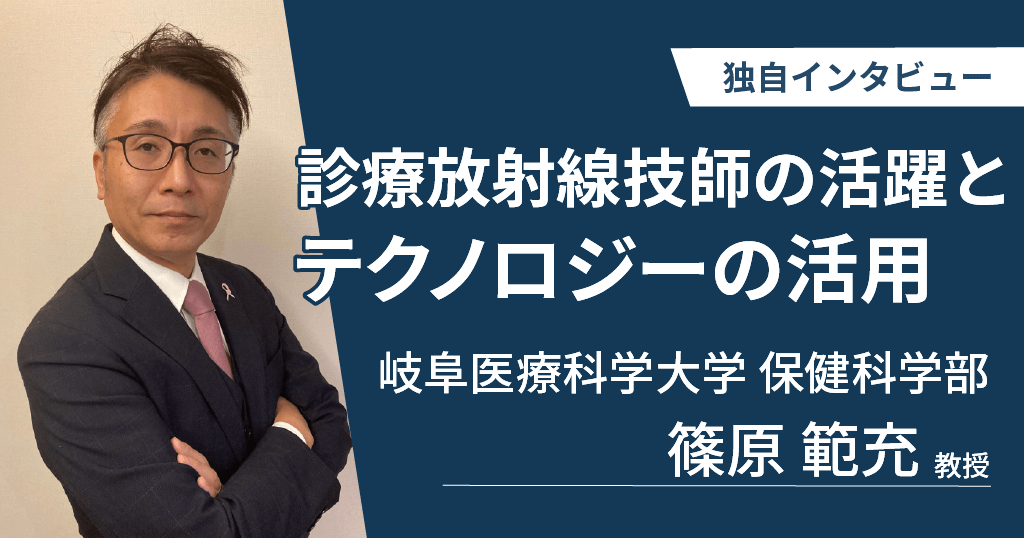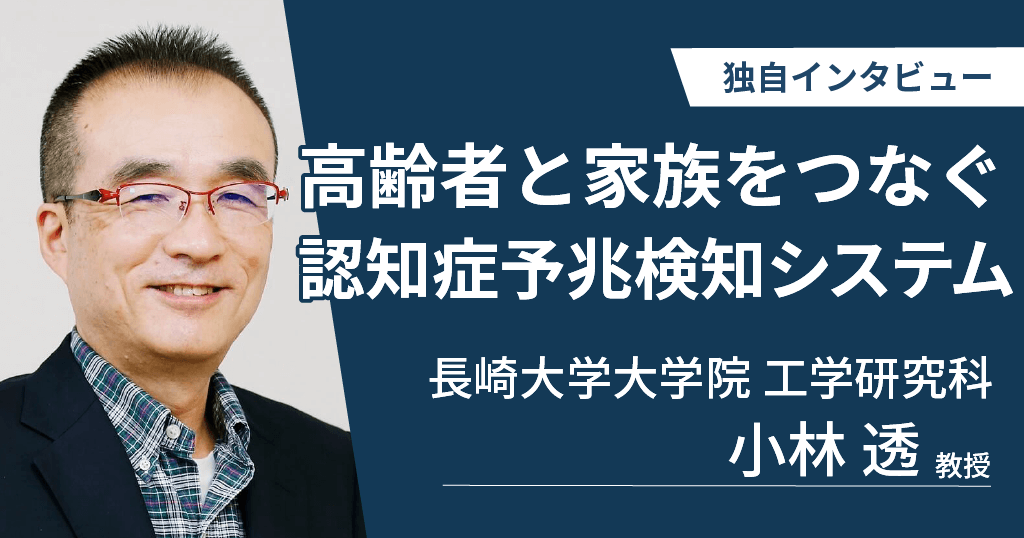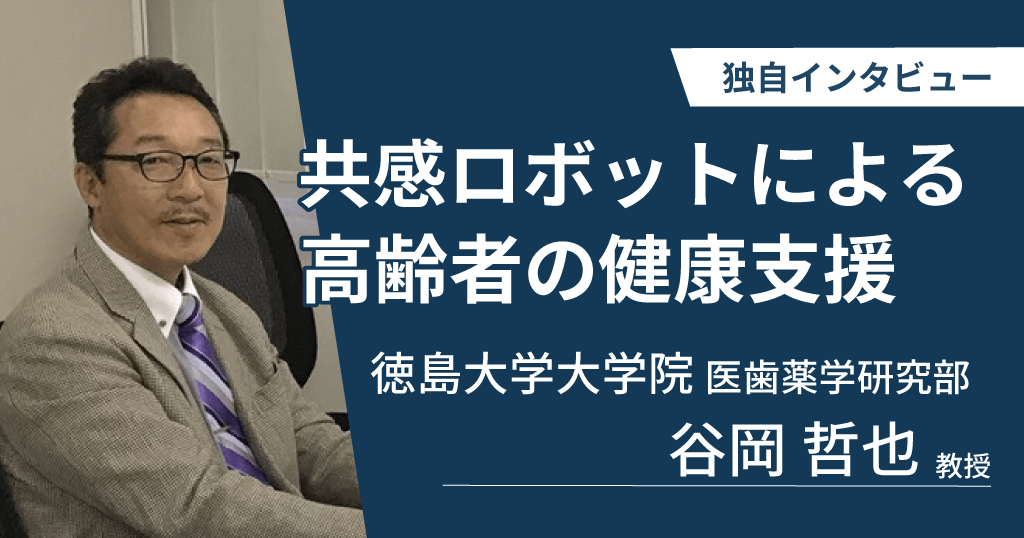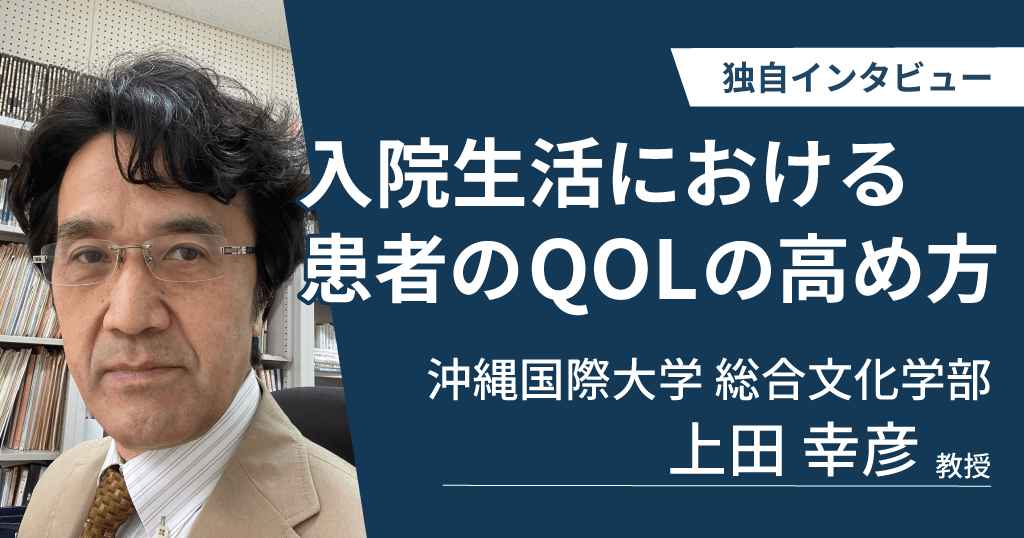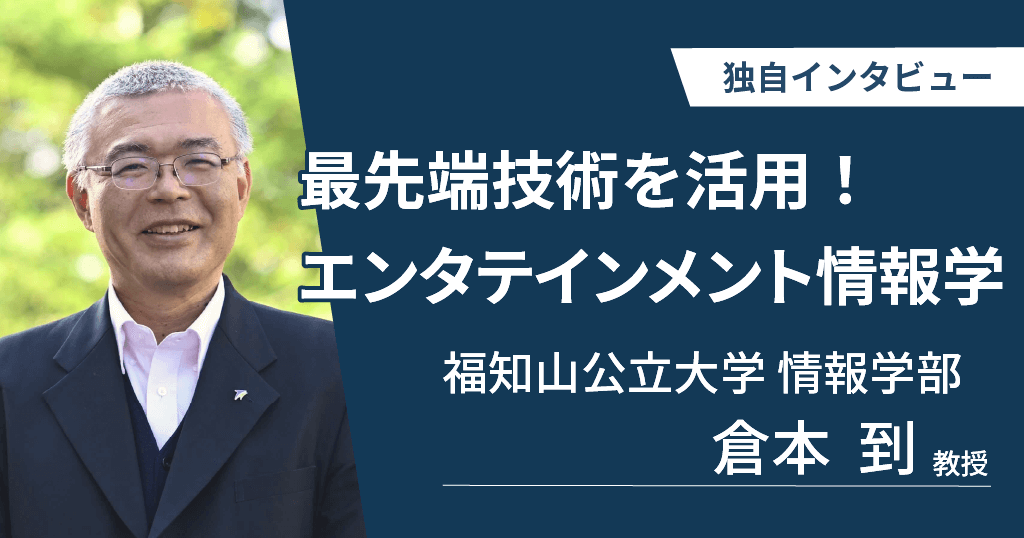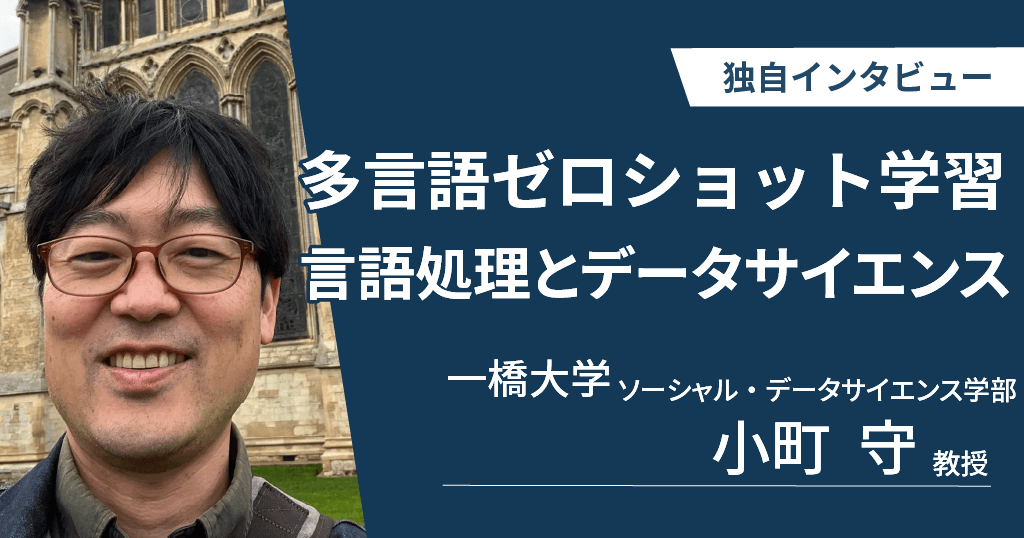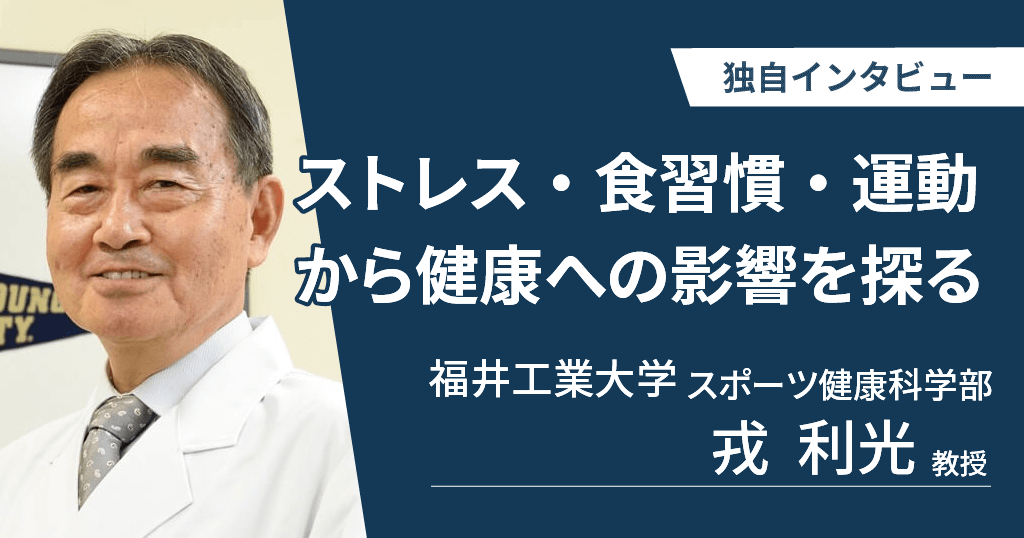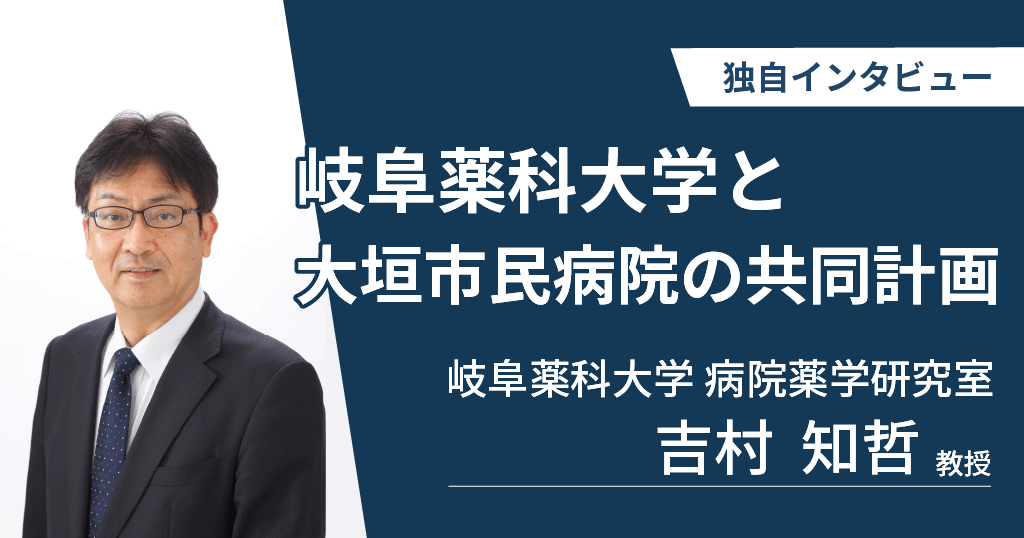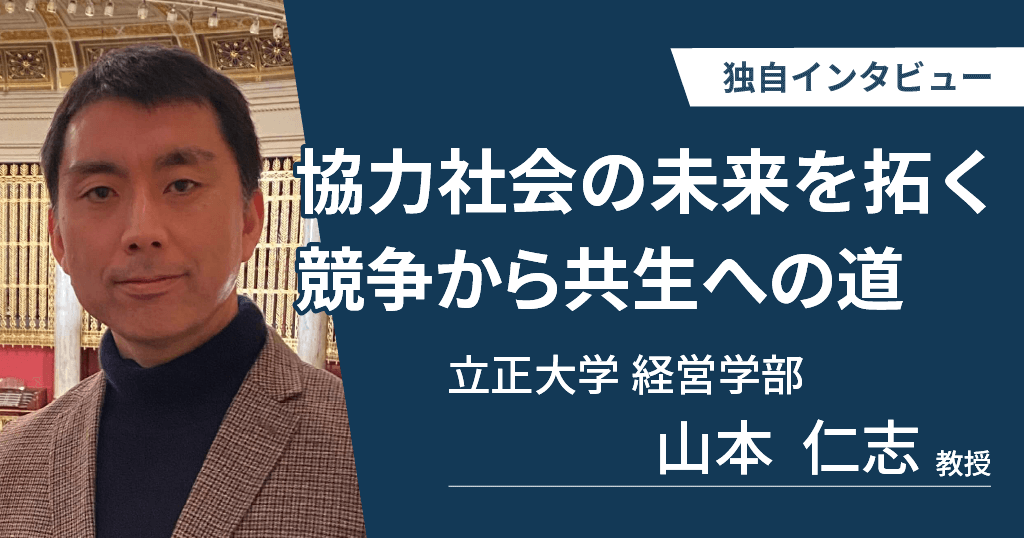大学教授・研究者・専門家・プロフェッショナルへのインタビュー– INTERVIEW –
大学教授などの研究者や専門家、プロフェッショナルをTLG GROUP編集部が「情報提供事業」の一環として直接取材し、その専門的な知識や研究成果を世の中へ広く伝える取り組みです。
メディア事業において長年の経験を持つTLG GROUPだからこそ、大学教授の素晴らしい専門的知識や研究成果を、学術の世界に留めることなく、できる限りライブ感のあるインタビュー記事として発信することができ、それがそのまま社会意義に繋がると考えています。
おかげさまで、当インタビューページは非常にアクセスが増えており、質の高い情報が大変多くの人に読まれ、届いています。インタビュー取材を快く引き受けていただいた大学教授の皆様には心より感謝申し上げます。
【>実際にインタビューさせていただくインタビュー事業部の紹介はこちら】
-

岐阜医療科学大学 篠原範充 教授【診療放射線技師の活躍とテクノロジーの活用】
会社や大学での定期健康診断でX線検査を受けたことがある方は多いのではないでしょうか。 そんなX線検査を担当しているのは、放射線を用いることで検査や治療を行う診療放射線技師と呼ばれる方々です。乳がん検診が注目されている中、診療放射線技師につい... -

高崎健康福祉大学 福地守 教授【ホタルの光から知の探究を目指す!脳内タンパク質「BDNF」の謎に迫る】
分子神経科学の分野では、細胞や分子に着目して、脳の未知なる領域への探求と、医療の未来を拓く可能性に焦点を当てた研究が進行中です。 この記事では、脳の機能に重要なタンパク質であるBDNF(brain-derived neurotrophic factor)に関する最新の研究に迫... -

長崎大学大学院 小林透 教授【認知症予兆検知システム|高齢者と家族のコミュニケーションを支える未来への一歩】
高齢化が進む中、認知症の発症リスクも増加しています。 この問題に対し、長崎大学大学院工学研究科の小林透教授率いる研究グループが開発した「認知症予兆検知システム」が注目を集めています。このシステムは、普段の生活行動から認知症の予兆を検知し、... -

徳島大学大学院 谷岡哲也 教授【看護と工学の融合「共感ロボット」が切り拓く高齢者の健康支援】
自律神経は、私たちの身体のバランスを維持する上で不可欠な役割を果たしています。特に高齢者では、自律神経のバランスが乱れることで疾患のリスクが高まります。このため、デイサービスなどで日常生活のサポートや機能訓練を受けることが生活リズムを整... -

沖縄国際大学 上田幸彦 教授【入院生活における患者のQOLを維持・高める方法とは?】
急な病気やけがで入院した際に、QOLを維持した生活ができるようになることは治療の質とどのような関係があるのでしょうか。 また、QOLを維持するために実際にどのようなアプローチが行われているのでしょうか。 この記事では、沖縄国際大学の上田幸彦教授... -

福知山公立大学 倉本到 教授【最先端技術を活用し楽しさを世の中に拡大するエンタテインメント情報学の魅力】
「エンタテイメント情報学」と聞くと、一般的には娯楽やゲームなどのイメージが強いかもしれませんが、実際にはこの分野は私たちの日常生活に密接に関わり、社会を豊かにし、楽しくするためのイノベーションが生まれる場でもあります。 また、近年のAIやデ... -

一橋大学 小町守 教授【多言語ゼロショット学習とは?言語処理とデータサイエンスの進化に迫る!】
データサイエンスの分野において、最近では「多言語ゼロショット学習」という革新的な手法が注目を集めています。この手法は、従来の自然言語処理の枠組みを超え、言語の壁を乗り越える可能性を秘めています。 同時に、対話型生成AIである「ChatGPT」など... -

福井工業大学 戎利光 教授【ストレス・食習慣・運動から健康への影響を探る】
一般的に、ストレスが増えると自律神経系が乱れ、身体の様々な機能に影響を及ぼすことが知られていますが、具体的にどのような悪影響があるのでしょうか。 また、健康を維持するには何を意識することが重要なのでしょうか。 この記事では、福井工業大学の... -

岐阜薬科大学 吉村知哲 教授【薬学と臨床の融合!岐阜薬科大学と大垣市民病院の連携がもたらす未来】
岐阜薬科大学は、薬学に特化した教育と研究に注力し、薬剤師や医療従事者の育成に力を入れています。 最近では、大垣市民病院との連携により、臨床薬学研究を推進するための「医療連携薬学研究室」が設立され話題になりました。 この記事では、大垣市民病... -

立正大学 山本仁志 教授【協力社会の未来を拓く!競争から共生への道】
社会的ジレンマは、個人の行動が社会全体に波及する現象であり、私たちの日常において、ごみのポイ捨てやコロナ禍における外出自粛、共有資源の浪費などとして頻繁に姿を現します。 また、この現象を解決するためには、協力が不可欠であり、その中でも「間...